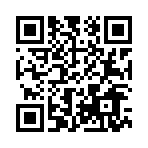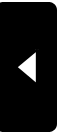2014年10月08日
北口本宮富士浅間神社
秩父華厳の滝の様子はこちらから!
本栖湖の様子はこちらから!
白糸の滝の様子はこちらから!
音止めの滝の様子はこちらから!
三保松原の様子はこちらから!
久能山東照宮の様子はこちらから!
富知六所浅間神社の様子はこちらから!
2014年 8月
富士山周りに数多く点在する浅間神社
こちらの浅間神社にも行きました

河口湖の向こうに富士山

北口本宮冨士浅間神社(wikiより)
山梨県富士吉田市上吉田にある神社。
旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。
祭神:木花開耶姫命
彦火瓊瓊杵命 - 夫神
大山祇神 - 父神
歴史
延暦7年(788年)に甲斐守である紀豊庭が現在地に社殿を造営したと伝わる。
中世には同社が所在する郡内地方の領主である小山田氏からの庇護を受けた。
社号について、甲斐国の地誌である『甲斐国志』では以下のように記される。
往古ヨリ此社中ヲ諏方ノ森ト称スルハ、浅間明神勧請セザル以前ヨリ諏方明神鎮座アル故ナリト云、古文書二諏方ノ森浅間明神トアル是ナリ
このように古来より社中に「諏訪の森」が位置し、諏訪神社の鎮座地に浅間神社を勧請したと伝わる。
現在当社は浅間神社であり祭神も木花開耶姫命を主祭神としているが、当初は諏訪神社であったと考えられている。
例えば天文17年(1548年)5月26日、小山田信有は吉田の諏訪禰宜に富士山神事の際に新宮を建てる場合は披露するように命じている。
このように富士山神事に関わる案件に対しても、諏訪禰宜に宛てがわれている。
永禄4年(1561年)3月2日、武田信玄は吉田の諏訪の森の木を伐ることを禁止している。
『甲斐国志』によると、同年に武田信玄が富士権現を造営したとある。
これらの事柄から、永禄4年(1561年)の信玄による富士権現造営が現在の北口本宮冨士浅間神社の元になるものであるとし、それ以前は諏訪社のみが鎮座していたとする見方がある。
その後は元和元年(1615年)、谷村城主鳥居土佐守成次が現在の本殿を建立、貞享5年(1688年)に社殿が造修された。
一時荒廃していたが、享保年間になって、富士講の行者であった村上光清が私財を投げ打って再興し、富士講の参詣者を集めた。
拝殿の前の両脇には樹齢千年の「富士太郎杉」「富士夫婦檜」の名を持つ大きな御神木がある。
富士登山道の吉田口の起点にあたる。
江戸時代には富士講が流行し、周辺には御師の宿坊が百件近く立ち並んだこともあるが、これは神社に属さない独自の宗教活動であった。
昭和初期には神社北の裏手から登山バス浅間神社 - 馬返線が運行していた。
同じ富士吉田市下吉田にある小室浅間神社に対して「上浅間」と呼ばれる事があるが、直接的な関係は無い。
富士吉田地域に於いて、この神社が前述した富士講御師に依る対外的な信仰を集め、下吉田の小室浅間は農耕信仰を中心として地元民の生活に根差した文化があった。
神社によくある杉の道

めっちゃ好きですね~
ゆっくり歩きながら空気を吸うだけで心が落ち着きます
二つ目の鳥居を通ります
立派な門の随神門
お祭りで使われてそうな神楽殿
手水舎
色んな所へ行っているうちに神社の作法も覚えてしまいました

北口本宮富士浅間神社には大きな木が沢山生えていて神社の見所になっています

冨士夫婦檜
幹周:7.65m 根回り:17.0m 樹高:33m 樹齢:約1000年
冨士太郎杉
幹周:8.2m 根回り:21.0m 樹高:30m 樹齢:約1000年
上吉田諏訪神社の大杉
幹周:9.40m 樹高:41m
巨木の数の多さで歴史のある神社だというのが分かります

昔は諏訪神社だったそうで諏訪神社の拝殿の所にある富士山型の神輿
吉田の火祭りの時に担がれる様です

行ったとき、拝殿は修復中でしたが、普通にお参りは出来ました

富士山へと続く鳥居
昔はここからお参りをして富士山を登っていたんでしょうね

Posted by gami at 00:58│Comments(0)
│旅
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。