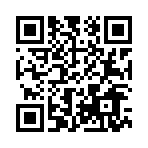2013年04月25日
原尻の滝
3月14日
祖母山登山の様子はこちらから!
 祖母山を下山し
祖母山を下山し
次に向かったのがこちら!
 原尻の滝
原尻の滝
幅120m、高さ20m
原尻の滝(はらじりのたき)は、大分県豊後大野市緒方町原尻の大野川水系緒方川にある滝です
日本の滝百選に選ばれています
田園に囲まれた平地に突如滝が現れるのが特徴で、「東洋のナイアガラ」と呼ばれています
先程、祖母山で見た雲のナイアガラに比べると、流石に規模は小さくなりますが、日本で幅が広い滝なんて、そうそう拝めるものでは無いので、凄く新鮮でした
しかも、近くにも幅100m、落差20mの「沈堕の滝」と言う幅広の滝もあるそうです(時間が無くて行けませんでしたが )
)
なんともナイアガラだらけの土地ですね~
 原尻の滝の下流には吊橋が掛かっています
原尻の滝の下流には吊橋が掛かっています
そこからの滝が一番のビュースポットと聞いておりましたが
 残念ながら、この時は工事中にて通行止めになっておりました
残念ながら、この時は工事中にて通行止めになっておりました
原尻の滝は、すぐ脇が道の駅になっています
ここに祖母山の山バッチが売っているので、祖母山登山の帰りに寄ってみるのも良いと思います(自分も、それで寄りました )
)
 かぼすソフトを戴き、次の目的地へと向かいます
かぼすソフトを戴き、次の目的地へと向かいます
祖母山登山の様子はこちらから!
次に向かったのがこちら!
幅120m、高さ20m
原尻の滝(はらじりのたき)は、大分県豊後大野市緒方町原尻の大野川水系緒方川にある滝です
日本の滝百選に選ばれています
田園に囲まれた平地に突如滝が現れるのが特徴で、「東洋のナイアガラ」と呼ばれています
先程、祖母山で見た雲のナイアガラに比べると、流石に規模は小さくなりますが、日本で幅が広い滝なんて、そうそう拝めるものでは無いので、凄く新鮮でした

しかも、近くにも幅100m、落差20mの「沈堕の滝」と言う幅広の滝もあるそうです(時間が無くて行けませんでしたが
 )
)なんともナイアガラだらけの土地ですね~

そこからの滝が一番のビュースポットと聞いておりましたが

原尻の滝は、すぐ脇が道の駅になっています
ここに祖母山の山バッチが売っているので、祖母山登山の帰りに寄ってみるのも良いと思います(自分も、それで寄りました
 )
)
2013年04月22日
祖母山
祖母山(1756m)
 祖母山(そぼさん)は、大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山であり、宮崎県の最高峰で日本百名山の一つです
祖母山(そぼさん)は、大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山であり、宮崎県の最高峰で日本百名山の一つです
神武天皇の皇祖母、豊玉姫(とよたまひめ)を祀ることからこの名があります
登り 2時間50分
下り 2時間5分
(北谷登山口より)
3月14日
初めての山域に行く時の、まず最初の不安があります
「登山口ってどこだろう、、、、、」という不安
あまりにも狭い道であったり、砂利道であったり、果てには凸凹な路面で車の底が当たる様な道であったり、、、、、
そんな道ですと、、、、、
 「この道であっているの?」 となります
「この道であっているの?」 となります
雨が降り、街灯なんてあるはずもない真っ暗で、上に書かれた事が全て該当するような道をひたすら進み、祖母山の北谷登山口を目指します
お隣の阿蘇山はかなり観光地化して俗っぽい山になっておりますが、この祖母山は、その点では阿蘇山とは正反対の山の様です(静かな山の方が好きなのですが)
そんな暗い狭い道だと色々とネガティブな方向に考えが及んでしまいます
もし対向車が来たら、どう避けよう、、、、、とか
道がもっと酷くなり、もし車がはまったりしたら、、、、、とか
そんな不安を抱えて車を走らせなければなりません
 所々にある小さい標識とヘッドライトの明かりだけが頼りです
所々にある小さい標識とヘッドライトの明かりだけが頼りです
それはまさに
「恐怖」
なのです
もし、いきなり道が無くなって川に落ちたりとかになったら!
もし、いきなり崖崩れが起きて生き埋めになったりしたら!!
うきゃあああああああああああ!!!
なんか建物がぁぁぁぁぁ!!!!
 あっ、着いた
あっ、着いた
登山口にあるトイレでした
エンジンを切り、目の前の手の平も見れない位の暗闇の中、就寝です
7:00 外の明るさと寒さで目を覚ましました
登山の準備をして
 7:30 祖母山登山スタートです
7:30 祖母山登山スタートです
登りは山頂まで一直線に登る風穴コースを登り、下山は緩やかな千間平コースから下る行程です
時間的には、どちらも同じ位の登山道になります
 風穴コースは最初、川を幾つか横切り次第に急になり手を使って崖を登るような少しワイルドな登山道になっております
風穴コースは最初、川を幾つか横切り次第に急になり手を使って崖を登るような少しワイルドな登山道になっております
 「風穴コース」という名の通り途中には夏でも氷が見れるという洞穴があります
「風穴コース」という名の通り途中には夏でも氷が見れるという洞穴があります
 8:20 その風穴に到着
8:20 その風穴に到着
 ちょっと入ってみましたが中は完全に凍っていた為、奥までは行けませんでした
ちょっと入ってみましたが中は完全に凍っていた為、奥までは行けませんでした
この先はアイゼンとロープが必携ですね~
そこから、少し進むと、まさかの景色に
 樹氷だ!
樹氷だ!
昨日の雨は夜のうちに雪になり、標高が高い所では樹氷になっていた様です
 九州の山で、この景色は良い意味で期待を裏切って戴きました
九州の山で、この景色は良い意味で期待を裏切って戴きました
 まるで白い花を咲かせたような木々
まるで白い花を咲かせたような木々
 その景色を楽しみながら歩きます
その景色を楽しみながら歩きます
頂上まで、あと少しの所まで来た時でした
今まで、ずっと曇っていた景色の中を一人、歩いていたのですが
スーっとガスが取れたのです
青空が見え、今まででも、出逢ったことの無いような景色と出逢ったのでした






そこには雲の滝が流れ落ちていました
片側では無く両脇で流れ落ちているのです
ナイアガラの滝
雲のナイアガラの滝なのです
幅、何km 落差、何百mにも、なるだろう雲のナイアガラ
雲が流れ落ち、流れ落ちたところの木々を樹氷にし白く染める
遠くは、果てなく続く雲海
空は、とても澄んだ青
その真ん中、雲のナイアガラの真ん中で、ただ一人立っているのです
とても、壮大で、力強く、やさしく、希望に満ち満ちた景色
そんな景色でした


下を見ると真っ白に染まる木々
自然の大きさに自然と涙が出て、ただ、ただ魅入るばかりでした
 9:30 祖母山山頂(1756m)に到着
9:30 祖母山山頂(1756m)に到着
 山頂の社
山頂の社


山頂にも木々には真っ白い花が咲き誇っておりました

遠くには一昨日に登った霧島山が浮かんでいました
 9:50 祖母山の九合目に建つ山小屋(その名もQ合目小屋)を通り
9:50 祖母山の九合目に建つ山小屋(その名もQ合目小屋)を通り
 10:20 国見峠を通り
10:20 国見峠を通り
 11:20 下山完了
11:20 下山完了
枯木に
白花咲かす
皇祖母かな
祖母山は花咲か爺ならぬ、花咲か婆だったようです
神武天皇の皇祖母、豊玉姫(とよたまひめ)を祀ることからこの名があります
登り 2時間50分
下り 2時間5分
(北谷登山口より)
3月14日
初めての山域に行く時の、まず最初の不安があります
「登山口ってどこだろう、、、、、」という不安
あまりにも狭い道であったり、砂利道であったり、果てには凸凹な路面で車の底が当たる様な道であったり、、、、、
そんな道ですと、、、、、
雨が降り、街灯なんてあるはずもない真っ暗で、上に書かれた事が全て該当するような道をひたすら進み、祖母山の北谷登山口を目指します

お隣の阿蘇山はかなり観光地化して俗っぽい山になっておりますが、この祖母山は、その点では阿蘇山とは正反対の山の様です(静かな山の方が好きなのですが)
そんな暗い狭い道だと色々とネガティブな方向に考えが及んでしまいます

もし対向車が来たら、どう避けよう、、、、、とか
道がもっと酷くなり、もし車がはまったりしたら、、、、、とか
そんな不安を抱えて車を走らせなければなりません
それはまさに
「恐怖」
なのです
もし、いきなり道が無くなって川に落ちたりとかになったら!
もし、いきなり崖崩れが起きて生き埋めになったりしたら!!
うきゃあああああああああああ!!!
なんか建物がぁぁぁぁぁ!!!!

登山口にあるトイレでした
エンジンを切り、目の前の手の平も見れない位の暗闇の中、就寝です

7:00 外の明るさと寒さで目を覚ましました

登山の準備をして

登りは山頂まで一直線に登る風穴コースを登り、下山は緩やかな千間平コースから下る行程です
時間的には、どちらも同じ位の登山道になります


この先はアイゼンとロープが必携ですね~
そこから、少し進むと、まさかの景色に
昨日の雨は夜のうちに雪になり、標高が高い所では樹氷になっていた様です



頂上まで、あと少しの所まで来た時でした
今まで、ずっと曇っていた景色の中を一人、歩いていたのですが
スーっとガスが取れたのです
青空が見え、今まででも、出逢ったことの無いような景色と出逢ったのでした
そこには雲の滝が流れ落ちていました
片側では無く両脇で流れ落ちているのです
ナイアガラの滝
雲のナイアガラの滝なのです
幅、何km 落差、何百mにも、なるだろう雲のナイアガラ
雲が流れ落ち、流れ落ちたところの木々を樹氷にし白く染める
遠くは、果てなく続く雲海
空は、とても澄んだ青
その真ん中、雲のナイアガラの真ん中で、ただ一人立っているのです
とても、壮大で、力強く、やさしく、希望に満ち満ちた景色
そんな景色でした
下を見ると真っ白に染まる木々
自然の大きさに自然と涙が出て、ただ、ただ魅入るばかりでした
山頂にも木々には真っ白い花が咲き誇っておりました

遠くには一昨日に登った霧島山が浮かんでいました

枯木に
白花咲かす
皇祖母かな
祖母山は花咲か爺ならぬ、花咲か婆だったようです

2013年04月20日
龍門滝
3月13日
開聞岳登山の様子はこちらから!
池田湖観光の様子はこちらから!
指宿温泉入浴の様子はこちらから!
続いての目的地は鹿児島県にある名瀑を見に行きました
 龍門滝
龍門滝
落差 46m 滝の幅 43m 水系 網掛川
 龍門滝(りゅうもんだき、りゅうもんのたき)は、鹿児島県姶良市加治木町に位置し、日本の滝百選にも選ばれています
龍門滝(りゅうもんだき、りゅうもんのたき)は、鹿児島県姶良市加治木町に位置し、日本の滝百選にも選ばれています
その昔、中国の人が「漢土の龍門の瀑(たき)を見るがごとし」と賞したところから、この名があると伝えられています
九州自動車道から見ることが出来る滝です
水量が極端に少なくなる時期もあるそうですが、見に行った時は水量も多く、豪快な滝でかなりの見応え!
 梅やつつじなどの花も咲き誇っており、滝と色鮮やかな花を満喫出来ました
梅やつつじなどの花も咲き誇っており、滝と色鮮やかな花を満喫出来ました
 深田久弥さんの百名山を読んでいると度々、目にする橘南渓の西遊記
深田久弥さんの百名山を読んでいると度々、目にする橘南渓の西遊記
その一節で絶賛されている滝とのことです
 もし近くに来たら見に行ってみて下さい
もし近くに来たら見に行ってみて下さい
水の落ちる音を聞きながら、ただ時が過ぎるのも良いものです
往さ来(くる)さ道行く人も暫(しば)しとて立ちかえり見る滝の白糸
第十八代藩主 島津家久
開聞岳登山の様子はこちらから!
池田湖観光の様子はこちらから!
指宿温泉入浴の様子はこちらから!
続いての目的地は鹿児島県にある名瀑を見に行きました

落差 46m 滝の幅 43m 水系 網掛川
その昔、中国の人が「漢土の龍門の瀑(たき)を見るがごとし」と賞したところから、この名があると伝えられています
九州自動車道から見ることが出来る滝です
水量が極端に少なくなる時期もあるそうですが、見に行った時は水量も多く、豪快な滝でかなりの見応え!


その一節で絶賛されている滝とのことです


水の落ちる音を聞きながら、ただ時が過ぎるのも良いものです
往さ来(くる)さ道行く人も暫(しば)しとて立ちかえり見る滝の白糸
第十八代藩主 島津家久
2013年04月18日
指宿温泉
3月13日
開聞岳登山と池田湖の大うなぎ観光を終え
開聞岳登山の様子はこちらから!
池田湖観光の様子はこちらから!
次に有名な温泉地、指宿温泉へと行って来ました
「指宿温泉」(wikiより)
宿温泉(いぶすきおんせん)は、鹿児島県指宿市東部(旧国薩摩国)にある摺ヶ浜温泉(砂蒸しで有名)、弥次ヶ湯温泉、二月田温泉などの温泉群の総称。
鹿児島県内有数の観光地であり、2003年(平成15年)において年間285万人の観光客が訪れ、91万人の宿泊客を集めている。
農業や養殖などへの温泉利用も盛んであり、温泉の9割が産業利用されていた時期もあった。また、1960年頃から始まったハネムーンブームの中、「東洋のハワイ」と呼ばれた指宿温泉は、そのメッカとして賑わった
泉質はおおむねナトリウム-塩化物泉であるが地域や掘削深度によって塩分濃度や微量成分が異なる。
活動泉源はおおむね500カ所。
一日あたりの総湧出量は約12万トン。
湧出温度は50-60℃が多いが、100℃に達するものもある。
温泉の水源は池田湖や鰻池に溜まった雨水と鹿児島湾からの海水が地下で混合したものであり、熱源は阿多カルデラに関連したマグマであると考えられている。
 砂に埋められる風呂、「砂蒸し風呂」で有名ですね~~
砂に埋められる風呂、「砂蒸し風呂」で有名ですね~~
 私も指宿入浴スタイル、砂蒸し風呂を体験して参りました
私も指宿入浴スタイル、砂蒸し風呂を体験して参りました
 日帰り砂蒸し風呂施設「砂楽」に入館~~♪
日帰り砂蒸し風呂施設「砂楽」に入館~~♪
受付を済ませ浴衣に着替え外に出ると
 分かりますか?
分かりますか?
砂浜から湯気が出ているのです
遠くからでも砂が温泉で温められていることが分かります
砂埋めポイントへ向かいます
ザクザクザクザク(埋められる音)
オ、オオオオオウ~~~
ぢねつ、地熱が!
温かくて気持ちいい~~
昨日からの登山で使った筋肉が和らいでいくぅ~~!
フフフフフゥゥゥゥゥ~~~~!
てな、感じで砂の入浴が出来ます
砂風呂は15分位が目安だそうです、それ以上続けると火傷などの原因になるそうです(地熱恐るべし)
砂風呂から出たあとは砂を落として、普通の風呂に入り汗を流しました
体がホクホクとして焼き芋の様になったところで次の目的地へと向かいます
開聞岳登山と池田湖の大うなぎ観光を終え
開聞岳登山の様子はこちらから!
池田湖観光の様子はこちらから!
次に有名な温泉地、指宿温泉へと行って来ました

「指宿温泉」(wikiより)
宿温泉(いぶすきおんせん)は、鹿児島県指宿市東部(旧国薩摩国)にある摺ヶ浜温泉(砂蒸しで有名)、弥次ヶ湯温泉、二月田温泉などの温泉群の総称。
鹿児島県内有数の観光地であり、2003年(平成15年)において年間285万人の観光客が訪れ、91万人の宿泊客を集めている。
農業や養殖などへの温泉利用も盛んであり、温泉の9割が産業利用されていた時期もあった。また、1960年頃から始まったハネムーンブームの中、「東洋のハワイ」と呼ばれた指宿温泉は、そのメッカとして賑わった
泉質はおおむねナトリウム-塩化物泉であるが地域や掘削深度によって塩分濃度や微量成分が異なる。
活動泉源はおおむね500カ所。
一日あたりの総湧出量は約12万トン。
湧出温度は50-60℃が多いが、100℃に達するものもある。
温泉の水源は池田湖や鰻池に溜まった雨水と鹿児島湾からの海水が地下で混合したものであり、熱源は阿多カルデラに関連したマグマであると考えられている。
 砂に埋められる風呂、「砂蒸し風呂」で有名ですね~~
砂に埋められる風呂、「砂蒸し風呂」で有名ですね~~


受付を済ませ浴衣に着替え外に出ると
砂浜から湯気が出ているのです

遠くからでも砂が温泉で温められていることが分かります
砂埋めポイントへ向かいます
ザクザクザクザク(埋められる音)
オ、オオオオオウ~~~

ぢねつ、地熱が!
温かくて気持ちいい~~

昨日からの登山で使った筋肉が和らいでいくぅ~~!
フフフフフゥゥゥゥゥ~~~~!
てな、感じで砂の入浴が出来ます

砂風呂は15分位が目安だそうです、それ以上続けると火傷などの原因になるそうです(地熱恐るべし)
砂風呂から出たあとは砂を落として、普通の風呂に入り汗を流しました

体がホクホクとして焼き芋の様になったところで次の目的地へと向かいます

2013年04月16日
池田湖
3月13日
開聞岳の登山を終え
(開聞岳の様子はこちらから!)
次に向かったのがコチラ
 池田湖パラダイス
池田湖パラダイス
と言われてもパッとしないと思うので
 池田湖
池田湖
池田湖(いけだこ)は、鹿児島県の薩摩半島南東部にある直径約3.5km、周囲約15km、ほぼ円形のカルデラ湖
九州最大の湖である
 湖面の標高は66m、深さは233mで、最深部は海抜-167mとなる
湖面の標高は66m、深さは233mで、最深部は海抜-167mとなる
湖底には直径約800m、湖底からの高さ約150mの湖底火山がある
池田湖を含む窪地地形は池田カルデラと呼ばれている
池田湖は古くは開聞の御池または神の御池と呼ばれており龍神伝説がある
 池田湖と言えば1960年代に生息が噂された巨大水棲生物の通称「イッシー」が有名です
池田湖と言えば1960年代に生息が噂された巨大水棲生物の通称「イッシー」が有名です
1978年には住民約20名により目撃されたこともあったそうですが
今はおとさたが無く、巨大な、ある生き物の見間違いとされています
その間違われた巨大生物が池田湖パラダイスで飼育されているのです!
そうです、あのニョロっとしてヌメッとして細長い、蒲焼にすると美味しい、、、、、、
 おはよウナギ!
おはよウナギ!
、、、、、、、、、、
 そう、これ!うなぎです!
そう、これ!うなぎです!
おおうなぎなのです!
大きいものになると2mを超えるそうで、それとイッシーを見間違えたのでは?と言うことです
 実際に見てみると、まさにモンスターでした
実際に見てみると、まさにモンスターでした
 もう、うなぎと言うよりライギョに近い図体をお持ちです
もう、うなぎと言うよりライギョに近い図体をお持ちです
一体、蒲焼き何人分なのかと、、、、、
ジュルリ、、、、、、
ってことで
 ちょうど飯時ということもあり
ちょうど飯時ということもあり
 早速!
早速!
(うわ美味しそう )
)
 いただきマウス!
いただきマウス!
完
開聞岳の登山を終え
(開聞岳の様子はこちらから!)
次に向かったのがコチラ
と言われてもパッとしないと思うので

池田湖(いけだこ)は、鹿児島県の薩摩半島南東部にある直径約3.5km、周囲約15km、ほぼ円形のカルデラ湖
九州最大の湖である
湖底には直径約800m、湖底からの高さ約150mの湖底火山がある
池田湖を含む窪地地形は池田カルデラと呼ばれている
池田湖は古くは開聞の御池または神の御池と呼ばれており龍神伝説がある

1978年には住民約20名により目撃されたこともあったそうですが
今はおとさたが無く、巨大な、ある生き物の見間違いとされています

その間違われた巨大生物が池田湖パラダイスで飼育されているのです!
そうです、あのニョロっとしてヌメッとして細長い、蒲焼にすると美味しい、、、、、、
 おはよウナギ!
おはよウナギ!、、、、、、、、、、
おおうなぎなのです!

大きいものになると2mを超えるそうで、それとイッシーを見間違えたのでは?と言うことです


一体、蒲焼き何人分なのかと、、、、、
ジュルリ、、、、、、

ってことで
(うわ美味しそう
 )
) いただきマウス!
いただきマウス! 完