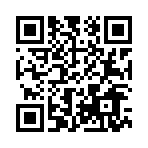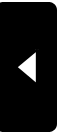2014年05月14日
丸岡城
2014年 4月
荒島岳登山の様子はこちらから!
龍双ヶ滝の様子はこちらから!
東尋坊の様子はこちらから!
雄島の様子はこちらから!
荒島岳登山旅に行っていたのが調度、4月の半ばで福井石川周辺は桜前線真っ只中
そんな時期なもんだから福井石川の桜の名所に行ってみようと、訪れたのが「丸岡城」でした
駐車場に車を停め、丘の上に建つ丸岡城を目指します

丁度、桜も満開で桜祭りをやっており、凄い人だかりになっておりました

丸岡城の桜祭りポスター

一年に一度、春に咲くからこその桜
日本の宝ですね

ピンク一色と言った感じ

階段を登り丘の上に出ると露店がやっており、たこ焼きを頂きました

どうやら、ここから白山は見えないみたいですね ついつい探してまう
ついつい探してまう

大きなしだれ桜も咲き始めておりました

今では堀は埋められておりますが、昔はこんな形だったらしいです

真ん中の天守閣へ向かいます
っと、天守閣に着いた所でで丸岡城の解説を、、、、、
丸岡城(wikiより)

福井県坂井市丸岡町霞にあった城である。
別名霞ヶ城。
江戸時代には丸岡藩の藩庁となった。
福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城である。
近世に山麓部分が増築され、周囲に五角形の内堀が廻らされていた。
安土桃山時代に建造されたと推定される天守は、国の重要文化財に指定されている。
その他、石垣が現存している。移築現存する建物として、小松市の興善寺および、あわら市の蓮正寺に、それぞれ城門、丸岡町野中山王の民家に、不明門と伝わる城門がある。
ほかに土塀が現存する。
五角形の内堀は現在埋め立てられているが、この内堀を復元する計画が浮上している。
「霞ヶ城」の名の由来は合戦時に大蛇が現れて霞を吹き、城を隠したという伝説による。
歴史・沿革

安土桃山時代・江戸時代[編集]1576年(天正4年) 織田信長の家臣で、越前ほぼ一帯を領していた柴田勝家の甥である勝豊により築城され、勝豊はそれまでの豊原寺城から当城に移った。
1582年(天正10年) 本能寺の変の後の清洲会議により、勝豊は近江国長浜城に移された。
代わって勝家は安井家清を城代として置いた。
1583年(天正11年) 柴田勝家が豊臣秀吉によって北ノ庄城で滅ぼされると、この地は丹羽長秀の所領となり、長秀は丸岡城主として青山宗勝(修理亮)を置いた。
1600年(慶長5年) 丹羽長秀死後、領地はそのままに豊臣秀吉の家臣となっていた青山宗勝とその子・忠元は、関ヶ原の戦いで敗者である西軍方につき改易された。
越前国には勝者の徳川家康の次男・結城秀康が入封し、丸岡城には秀康家臣の今村盛次が2万6千石を与えられ入城した。
1612年(慶長17年) 今村盛次は越前騒動に連座し失脚した。幕府より附家老として福井藩に附せられた本多成重が4万3千石で新たな城主となった。
1624年(寛永元年) 福井藩二代目の松平忠直が、不行跡を理由に豊後配流となり、福井藩に減封などの処分が下された。
同時に本多成重は福井藩より独立。大名に列し丸岡藩が成立した。
1695年(元禄8年) 4代重益の治世、本多家の丸岡藩でお家騒動が起こり、幕府の裁定により改易となった。
代わって有馬清純が越後国糸魚川藩より5万石で入城。以後、有馬氏丸岡藩6代の居城となり明治維新を迎えた。
1871年(明治4年) 廃藩置県により廃城となり天守以外全て解体された。
1901年(明治34年) 残された天守は、丸岡町により買い戻され解体を免れ、城跡は公園となった。
本丸を囲んでいた堀は、大正後期から昭和初期までの間に徐々に埋められ消滅した。
1934年(昭和9年) 天守が国宝保存法(旧法)に基づく国宝に指定される。
1948年(昭和23年) 福井地震のために倒壊。
1950年(昭和25年) 文化財保護法(新法)施行により天守は重要文化財に指定される。
1955年(昭和30年) 倒壊した天守は倒壊材を元の通り組み直し修復された。
1990年(平成2年) 「霞ヶ城公園」として日本さくら名所100選に選定された。
2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(36番)に選定された。
っと、言う事で中に入って見学してみました
中にはジオラマが作られていたり、丸岡城の歴史を学ぶことが出来ます

更に、角度が90度近い、超急な階段を登り2階、3階へと登る事が出来ます

階段は登山道で言うと鎖場です、、、、、
桜祭りもあって、かなりの行列
階段を登るのに15分程待つことになりました

やっとこさ階段を上がり最上階の3階へ

景色を楽しみます 殿様気分を味わえます
殿様気分を味わえます

タ〇ロはどこじゃ!?

景色を楽しんだ後、行列の下りを終え、人でごったかえす天守閣をなんとか脱出
なんともまぁ
ホント桜とお城って、合いますね~

荒島岳登山の様子はこちらから!
龍双ヶ滝の様子はこちらから!
東尋坊の様子はこちらから!
雄島の様子はこちらから!
荒島岳登山旅に行っていたのが調度、4月の半ばで福井石川周辺は桜前線真っ只中

そんな時期なもんだから福井石川の桜の名所に行ってみようと、訪れたのが「丸岡城」でした

駐車場に車を停め、丘の上に建つ丸岡城を目指します
丁度、桜も満開で桜祭りをやっており、凄い人だかりになっておりました

丸岡城の桜祭りポスター
一年に一度、春に咲くからこその桜

日本の宝ですね

ピンク一色と言った感じ

階段を登り丘の上に出ると露店がやっており、たこ焼きを頂きました

どうやら、ここから白山は見えないみたいですね
 ついつい探してまう
ついつい探してまう大きなしだれ桜も咲き始めておりました
今では堀は埋められておりますが、昔はこんな形だったらしいです

真ん中の天守閣へ向かいます
っと、天守閣に着いた所でで丸岡城の解説を、、、、、

丸岡城(wikiより)
福井県坂井市丸岡町霞にあった城である。
別名霞ヶ城。
江戸時代には丸岡藩の藩庁となった。
福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城である。
近世に山麓部分が増築され、周囲に五角形の内堀が廻らされていた。
安土桃山時代に建造されたと推定される天守は、国の重要文化財に指定されている。
その他、石垣が現存している。移築現存する建物として、小松市の興善寺および、あわら市の蓮正寺に、それぞれ城門、丸岡町野中山王の民家に、不明門と伝わる城門がある。
ほかに土塀が現存する。
五角形の内堀は現在埋め立てられているが、この内堀を復元する計画が浮上している。
「霞ヶ城」の名の由来は合戦時に大蛇が現れて霞を吹き、城を隠したという伝説による。
歴史・沿革
安土桃山時代・江戸時代[編集]1576年(天正4年) 織田信長の家臣で、越前ほぼ一帯を領していた柴田勝家の甥である勝豊により築城され、勝豊はそれまでの豊原寺城から当城に移った。
1582年(天正10年) 本能寺の変の後の清洲会議により、勝豊は近江国長浜城に移された。
代わって勝家は安井家清を城代として置いた。
1583年(天正11年) 柴田勝家が豊臣秀吉によって北ノ庄城で滅ぼされると、この地は丹羽長秀の所領となり、長秀は丸岡城主として青山宗勝(修理亮)を置いた。
1600年(慶長5年) 丹羽長秀死後、領地はそのままに豊臣秀吉の家臣となっていた青山宗勝とその子・忠元は、関ヶ原の戦いで敗者である西軍方につき改易された。
越前国には勝者の徳川家康の次男・結城秀康が入封し、丸岡城には秀康家臣の今村盛次が2万6千石を与えられ入城した。
1612年(慶長17年) 今村盛次は越前騒動に連座し失脚した。幕府より附家老として福井藩に附せられた本多成重が4万3千石で新たな城主となった。
1624年(寛永元年) 福井藩二代目の松平忠直が、不行跡を理由に豊後配流となり、福井藩に減封などの処分が下された。
同時に本多成重は福井藩より独立。大名に列し丸岡藩が成立した。
1695年(元禄8年) 4代重益の治世、本多家の丸岡藩でお家騒動が起こり、幕府の裁定により改易となった。
代わって有馬清純が越後国糸魚川藩より5万石で入城。以後、有馬氏丸岡藩6代の居城となり明治維新を迎えた。
1871年(明治4年) 廃藩置県により廃城となり天守以外全て解体された。
1901年(明治34年) 残された天守は、丸岡町により買い戻され解体を免れ、城跡は公園となった。
本丸を囲んでいた堀は、大正後期から昭和初期までの間に徐々に埋められ消滅した。
1934年(昭和9年) 天守が国宝保存法(旧法)に基づく国宝に指定される。
1948年(昭和23年) 福井地震のために倒壊。
1950年(昭和25年) 文化財保護法(新法)施行により天守は重要文化財に指定される。
1955年(昭和30年) 倒壊した天守は倒壊材を元の通り組み直し修復された。
1990年(平成2年) 「霞ヶ城公園」として日本さくら名所100選に選定された。
2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(36番)に選定された。
っと、言う事で中に入って見学してみました

中にはジオラマが作られていたり、丸岡城の歴史を学ぶことが出来ます
更に、角度が90度近い、超急な階段を登り2階、3階へと登る事が出来ます
階段は登山道で言うと鎖場です、、、、、
桜祭りもあって、かなりの行列
階段を登るのに15分程待つことになりました

やっとこさ階段を上がり最上階の3階へ
景色を楽しみます
 殿様気分を味わえます
殿様気分を味わえますタ〇ロはどこじゃ!?

景色を楽しんだ後、行列の下りを終え、人でごったかえす天守閣をなんとか脱出

なんともまぁ
ホント桜とお城って、合いますね~

Posted by gami at 02:09│Comments(0)
│旅
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。