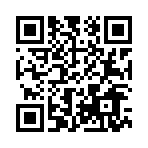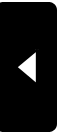2012年06月22日
大峰山 八経ヶ岳
八経ヶ岳(1915m)
 八経ヶ岳は奈良県吉野郡天川村と上北山村の境に位置し、修験者の道、大峯奥駈道の一部で近畿地方の最高峰です
八経ヶ岳は奈良県吉野郡天川村と上北山村の境に位置し、修験者の道、大峯奥駈道の一部で近畿地方の最高峰です
山上ヶ岳から一帯を含めて「大峰山」(日本百名山)とも呼ばれております
大峰山の山上ヶ岳(1719m)は日本で唯一、現在でも女人禁制が守られている山です
登り 3時間
下り 2時間20分
(行者還トンネルから)
紀伊半島の最高峰である大峰山 八経ヶ岳へと登山をして参りました
大峰山と言えば奥駈道ですね~~

大峯奥駈道とは? (wikiより)
大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)は、吉野と熊野を結ぶ大峯山を縦走する、修験道の修行の道。
2002年(平成14年)12月19日、国の史跡「大峯奥駈道」として指定され、2004年(平成16年)7月、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録された。
本来、大峯山寺より奥の「靡」に進むことを奥駈と云われていた。
修行場は「靡」(なびき)と呼ばれ、ひとつひとつに番号が割り当てられている。
すなわち、熊野本宮大社の本宮証誠殿(1番)にはじまり、吉野川河岸の柳の宿(75番)に終わる。
この大峯七十五靡は75箇所を数えるが、これは歴史的に整理されてきた結果であり、もっと多くの靡が設けられていた時期もある
大峯七十五靡
第75 柳の宿(やなぎのしゅく)
第74 丈六山(じょうろくさん)
第73 吉野山(よしのさん)
第72 水分神社(みくまりじんじゃ)
第71 金峯神社(きんぷじんじゃ)
第70 愛染の宿(あいぜんのしゅく)
第69 二蔵宿(にぞうのしゅく)
第68 浄心門(じょうしんもん)
第67 山上岳(さんじょうがたけ)
第66 小篠の宿(おざさのしゅく)
第65 阿弥陀森(あみだがもり)
第64 脇の宿(わきのしゅく)
第63 普賢岳(ふげんだけ)
第62 笙の窟(しょうのいわや)
第61 弥勒岳(みろくだけ)
第60 稚児泊(ちごどまり)
第59 七曜岳(しちようだけ)
第58 行者還(ぎょうじゃがえり)
第57 一の多和(いちのたわ)
第56 石休宿(いしやすみのしゅく)
第55 講婆世宿(こうばせのしゅく)
第54 弥山(みせん)
第53 朝鮮ヶ岳(ちょうせんがたけ)
第52 古今宿(ふるいまじゅく)
第51 八経ヶ岳(はっきょうがたけ)
第50 明星ヶ岳
第49 菊の窟(きくのいわや)
第48 禅師の森(ぜんじのもり)
第47 五鈷嶺(ごこのみね)
第46 舟の多和(ふねのたわ)
第45 七面山(しちめんさん)
第44 楊枝の宿(ようじのしゅく)
第43 仏性ヶ岳(ぶっしょうがたけ)
第42 孔雀岳(くじゃくだけ)
第41 空鉢岳(くうはちだけ)
第40 釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)
第39 都津門(とつもん)
第38 深仙宿(じんせんのしゅく)
第37 聖天の森(しょうてんのもり)
第36 五角仙(ごかくせん)
第35 大日岳(だいにちだけ)
第34 千手岳(せんじゅだけ)
第33 二つ岩(ふたついわ)
第32 蘇莫岳(そばくさだけ)
第31 小池宿(こいけのしゅく)
第30 千草岳(ちぐさだけ)
第29 前鬼山(ぜんきさん)
第28 前鬼三重滝(ぜんきのさんじゅうのたき)
第27 奥森岳(おくもりだけ)
第26 子守岳(こもりだけ)
第25 般若岳(はんにゃだけ)
第24 涅槃岳(ねはんだけ)
第23 乾光門(けんこうもん)
第22 持経宿(じきょうのしゅく)
第21 平治宿(へいじのしゅく)
第20 怒田宿(ぬたのしゅく)
第19 行仙岳(ぎょうせんだけ)
第18 笠捨山(かさすてやま)
第17 槍ヶ岳(やりがたけ)
第16 四阿宿(しあのしゅく)
第15 菊ヶ池
第14 拝返し(おがみかえし)
第13 香精山(こうしょうざん)
第12 古屋宿(ふるやのしゅく)
第11 如意珠岳(にょいじゅがだけ)
第10 玉置山(たまきさん)
第9 水呑宿(みずのみのしゅく)
第8 岸の宿(きしのしゅく)
第7 五大尊岳(ごだいそんだけ)
第6 金剛多和(こんごうたわ)
第5 大黒岳(だいこくだけ)
第4 吹越山(ふきこしやま)
第3 新宮(熊野速玉大社)
第2 那智山(なちさん、熊野那智大社)
第1 本宮大社(本宮証誠殿)
いやはや、、、、、
な、長ぇぇ~~~、、、、、
本宮から吉野に向かう順峯(じゅんぷ)、他方は、逆に吉野から本宮に向かう逆峯(ぎゃくふ)と呼ばれ今では逆峯、吉野から入るのが「一般的かつ正統的なもの」とされているそうです
え~~と、要は修行の為に約170kmの険しい山岳地帯を何日も掛けて歩くのです
これは今でも行われております
断崖絶壁に身を乗り出して修行してる所が有名ですね~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5月30日
夜のうちに駐車場まで来て就寝 (流石奈良県、鹿居すぎです、、、道中、何回か轢きそうになった、、、 )
)
そして、朝5時半頃、起床
 駐車場脇には綺麗な滝♪
駐車場脇には綺麗な滝♪
 こちらが行者還トンネルです
こちらが行者還トンネルです
国道309号線になるのですが、この辺の道路全般に言えるのですが道幅は狭く、雨や土砂崩れ等でよく通行止めになったりするので、事前にチェックをした方が良いと思います
(実際、この日の午後過ぎには、この道は工事の為、通行止めになりました)
 6:15 準備を終え、スタート!
6:15 準備を終え、スタート!
 登山道は綺麗な新緑に包まれておりました
登山道は綺麗な新緑に包まれておりました
 暫く登り高度を上げるとシャクナゲが咲き誇っておりました
暫く登り高度を上げるとシャクナゲが咲き誇っておりました
写真では分かり辛いですが奥に一杯ピンク色の花が咲いています
 6:55 奥駆道出合に到着
6:55 奥駆道出合に到着
山の稜線になり、ここから修験者の道、大峯奥駆道に合流します
 7:20 弁天の森を通過
7:20 弁天の森を通過
ここは良い休憩ポイントですね~
 ここまで来ると目指す弥山と八経ヶ岳が見えてきます
ここまで来ると目指す弥山と八経ヶ岳が見えてきます
左のとんがった山が八経で真ん中のこんもりした山が弥山です
 7:45 聖宝ノ宿跡に着きました
7:45 聖宝ノ宿跡に着きました
こちらの行者さんの像、昔から「理源大師像に触れてはならぬ」との言い伝えがあるとかなんとか、、、、、自分はバチ当たりな事はせず、手を合わせておきました
 流石、日本最大級の台風の通り道
流石、日本最大級の台風の通り道
倒木があちらこちらに有りました
 高度が上がると周りの景色も楽しむ事が出来ます
高度が上がると周りの景色も楽しむ事が出来ます

 弥山への最後の登りからの景色
弥山への最後の登りからの景色
 8:20 弥山(1895m)に到着
8:20 弥山(1895m)に到着
 弥山頂上には山小屋があり宿泊したりテントを張ったり出来ます
弥山頂上には山小屋があり宿泊したりテントを張ったり出来ます
この日は閉まっておりましたが、、、、、
閉まっていた場合、山バッヂは309号の道沿いの天川川合の十字路にある、「かどや食堂」さんで買うしか無いみたいです(その節はお世話になりました!是非とんかつ定食も食べて行きましょう! )
)
 弥山の頂上にある、お宮
弥山の頂上にある、お宮
 大峰山最高峰の八経ヶ岳、別名、八剣山(こっちの名前の方がカッコイイ!?
大峰山最高峰の八経ヶ岳、別名、八剣山(こっちの名前の方がカッコイイ!? )に向かいます
)に向かいます
 弥山から大体、30分程で八経ヶ岳頂上へと行けます
弥山から大体、30分程で八経ヶ岳頂上へと行けます
 途中にはオオヤマレンゲ自生地があります
途中にはオオヤマレンゲ自生地があります
 この時はまだ蕾でしたが時期になったらこの辺一帯、綺麗なんでしょうね~~
この時はまだ蕾でしたが時期になったらこの辺一帯、綺麗なんでしょうね~~
 丹沢と同じく、問題になっている位、鹿が住み着いているので、貴重な木花を守る為にフェンスが敷いてあります
丹沢と同じく、問題になっている位、鹿が住み着いているので、貴重な木花を守る為にフェンスが敷いてあります
 ドアを開け、奥へと進み、、、、、
ドアを開け、奥へと進み、、、、、
 9:00 紀伊半島のテッペン
9:00 紀伊半島のテッペン
八経ヶ岳(1915m)頂上へ到着~~♪
 頂上には錫杖が突き刺さっております
頂上には錫杖が突き刺さっております
そして頂上からの景色です♪

 禅師ノ森方面
禅師ノ森方面
 弥山と奥駈道、前半の山々
弥山と奥駈道、前半の山々
奥に山上ヶ岳
 奥駈道、後半の山々
奥駈道、後半の山々
奥に200名山の釈迦ヶ岳かな?
 紀伊半島のもうひとつの百名山の大台ヶ原を遠望~~♪
紀伊半島のもうひとつの百名山の大台ヶ原を遠望~~♪
 頂上の景色を楽しんだ後、早々に下山です
頂上の景色を楽しんだ後、早々に下山です
 11:00 下山を完了~~
11:00 下山を完了~~
下に着いた時には駐車場は満車状態でした
いや~~、楽しかった!!
良かった良かった~~
そして、早々に大台ヶ原へと向かうのでした(笑)
山上ヶ岳から一帯を含めて「大峰山」(日本百名山)とも呼ばれております
大峰山の山上ヶ岳(1719m)は日本で唯一、現在でも女人禁制が守られている山です
登り 3時間
下り 2時間20分
(行者還トンネルから)
紀伊半島の最高峰である大峰山 八経ヶ岳へと登山をして参りました

大峰山と言えば奥駈道ですね~~

大峯奥駈道とは? (wikiより)
大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)は、吉野と熊野を結ぶ大峯山を縦走する、修験道の修行の道。
2002年(平成14年)12月19日、国の史跡「大峯奥駈道」として指定され、2004年(平成16年)7月、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録された。
本来、大峯山寺より奥の「靡」に進むことを奥駈と云われていた。
修行場は「靡」(なびき)と呼ばれ、ひとつひとつに番号が割り当てられている。
すなわち、熊野本宮大社の本宮証誠殿(1番)にはじまり、吉野川河岸の柳の宿(75番)に終わる。
この大峯七十五靡は75箇所を数えるが、これは歴史的に整理されてきた結果であり、もっと多くの靡が設けられていた時期もある
大峯七十五靡
第75 柳の宿(やなぎのしゅく)
第74 丈六山(じょうろくさん)
第73 吉野山(よしのさん)
第72 水分神社(みくまりじんじゃ)
第71 金峯神社(きんぷじんじゃ)
第70 愛染の宿(あいぜんのしゅく)
第69 二蔵宿(にぞうのしゅく)
第68 浄心門(じょうしんもん)
第67 山上岳(さんじょうがたけ)
第66 小篠の宿(おざさのしゅく)
第65 阿弥陀森(あみだがもり)
第64 脇の宿(わきのしゅく)
第63 普賢岳(ふげんだけ)
第62 笙の窟(しょうのいわや)
第61 弥勒岳(みろくだけ)
第60 稚児泊(ちごどまり)
第59 七曜岳(しちようだけ)
第58 行者還(ぎょうじゃがえり)
第57 一の多和(いちのたわ)
第56 石休宿(いしやすみのしゅく)
第55 講婆世宿(こうばせのしゅく)
第54 弥山(みせん)
第53 朝鮮ヶ岳(ちょうせんがたけ)
第52 古今宿(ふるいまじゅく)
第51 八経ヶ岳(はっきょうがたけ)
第50 明星ヶ岳
第49 菊の窟(きくのいわや)
第48 禅師の森(ぜんじのもり)
第47 五鈷嶺(ごこのみね)
第46 舟の多和(ふねのたわ)
第45 七面山(しちめんさん)
第44 楊枝の宿(ようじのしゅく)
第43 仏性ヶ岳(ぶっしょうがたけ)
第42 孔雀岳(くじゃくだけ)
第41 空鉢岳(くうはちだけ)
第40 釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)
第39 都津門(とつもん)
第38 深仙宿(じんせんのしゅく)
第37 聖天の森(しょうてんのもり)
第36 五角仙(ごかくせん)
第35 大日岳(だいにちだけ)
第34 千手岳(せんじゅだけ)
第33 二つ岩(ふたついわ)
第32 蘇莫岳(そばくさだけ)
第31 小池宿(こいけのしゅく)
第30 千草岳(ちぐさだけ)
第29 前鬼山(ぜんきさん)
第28 前鬼三重滝(ぜんきのさんじゅうのたき)
第27 奥森岳(おくもりだけ)
第26 子守岳(こもりだけ)
第25 般若岳(はんにゃだけ)
第24 涅槃岳(ねはんだけ)
第23 乾光門(けんこうもん)
第22 持経宿(じきょうのしゅく)
第21 平治宿(へいじのしゅく)
第20 怒田宿(ぬたのしゅく)
第19 行仙岳(ぎょうせんだけ)
第18 笠捨山(かさすてやま)
第17 槍ヶ岳(やりがたけ)
第16 四阿宿(しあのしゅく)
第15 菊ヶ池
第14 拝返し(おがみかえし)
第13 香精山(こうしょうざん)
第12 古屋宿(ふるやのしゅく)
第11 如意珠岳(にょいじゅがだけ)
第10 玉置山(たまきさん)
第9 水呑宿(みずのみのしゅく)
第8 岸の宿(きしのしゅく)
第7 五大尊岳(ごだいそんだけ)
第6 金剛多和(こんごうたわ)
第5 大黒岳(だいこくだけ)
第4 吹越山(ふきこしやま)
第3 新宮(熊野速玉大社)
第2 那智山(なちさん、熊野那智大社)
第1 本宮大社(本宮証誠殿)
いやはや、、、、、
な、長ぇぇ~~~、、、、、

本宮から吉野に向かう順峯(じゅんぷ)、他方は、逆に吉野から本宮に向かう逆峯(ぎゃくふ)と呼ばれ今では逆峯、吉野から入るのが「一般的かつ正統的なもの」とされているそうです

え~~と、要は修行の為に約170kmの険しい山岳地帯を何日も掛けて歩くのです

これは今でも行われております
断崖絶壁に身を乗り出して修行してる所が有名ですね~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5月30日
夜のうちに駐車場まで来て就寝 (流石奈良県、鹿居すぎです、、、道中、何回か轢きそうになった、、、
 )
)そして、朝5時半頃、起床

国道309号線になるのですが、この辺の道路全般に言えるのですが道幅は狭く、雨や土砂崩れ等でよく通行止めになったりするので、事前にチェックをした方が良いと思います

(実際、この日の午後過ぎには、この道は工事の為、通行止めになりました)



写真では分かり辛いですが奥に一杯ピンク色の花が咲いています

山の稜線になり、ここから修験者の道、大峯奥駆道に合流します
ここは良い休憩ポイントですね~

左のとんがった山が八経で真ん中のこんもりした山が弥山です
こちらの行者さんの像、昔から「理源大師像に触れてはならぬ」との言い伝えがあるとかなんとか、、、、、自分はバチ当たりな事はせず、手を合わせておきました

倒木があちらこちらに有りました


この日は閉まっておりましたが、、、、、
閉まっていた場合、山バッヂは309号の道沿いの天川川合の十字路にある、「かどや食堂」さんで買うしか無いみたいです(その節はお世話になりました!是非とんかつ定食も食べて行きましょう!
 )
) )に向かいます
)に向かいます
八経ヶ岳(1915m)頂上へ到着~~♪
そして頂上からの景色です♪
奥に山上ヶ岳
奥に200名山の釈迦ヶ岳かな?
下に着いた時には駐車場は満車状態でした

いや~~、楽しかった!!
良かった良かった~~

そして、早々に大台ヶ原へと向かうのでした(笑)
Posted by gami at 00:19│Comments(0)
│山登り-近畿
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |