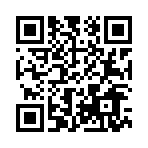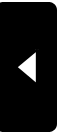2013年05月21日
殺生石
2013年 4月
那須岳登山へ行く、ついでに近辺の観光と滝巡りをして来ました
那須と言えば昔から定番のスポット
 殺生石
殺生石
栃木県那須町の那須湯本温泉付近にある火山性の噴気活動をしている場所です
硫黄の匂いがプンプンします
 4月も半ばでしたが寒気が入り込み前日に積雪があり、真っ白
4月も半ばでしたが寒気が入り込み前日に積雪があり、真っ白
なんとも、いかにもな名前の石は駐車場から2,3分、歩いた所にあります
途中には、云われのあるモニュメントが幾つかあります
 盲蛇石
盲蛇石
昔、湯守の五左ェ門さんが山に薪を採りに行き、この殺生河原で一休みしていると、2メートルを越える大きな蛇に出会いました。
大きな蛇の目は白く濁り盲の蛇で、かわいそうに思った五左ェ門さんは、これでは冬を越せないだろうと蛇のためにススキと小枝で小屋を作ってあげました。
次の年、五左ェ門さんは、湯殿開きの日に小屋に来て蛇をさがしましたが、蛇の姿はどこにもなく、かわりにキラキラと輝く湯の花がありました。
盲蛇に対する暖かい気持が神に通じ、湯の花のつくり方を教えてくれたのでした。
その後、湯の花のつくり方は村中に広まり、村人は盲蛇に対する感謝の気持を忘れず、蛇の首に似たこの石を盲蛇石を名付け大切にしたのだそうです。
生き物は大切にってことですね
 教伝地獄
教伝地獄
昔、「教傅(伝)」と言う住職がおりました。
この教傅は生まれながらの不良少年で、心配した母がお坊さんにしようとしてこの寺に預かってもらいました。
その教傅も二十八歳になって、前の住職の跡を継ぎ、母と一緒に寺に住むようになりましたが、その行いは少しも直りませんでした。
教傅は二、三人の友人と一緒に、那須温泉に湯治に行くことになりました。
教傅は、母が朝食を用意して進めると、まだ旅路支度も出来ていないのにと悪口を言いながら、お腹をけとばしてそのまま出発してしまいました。
那須温泉に着いた教傅達はある日殺生石を見学しようと賽の河原付近まで行くと、今まで晴れわたっていた空が、俄かにかきくもり雷鳴が天地を揺るがし、大地から火災熱湯が噴出し、連れの友人はいっせいに逃げ去りましたが、教傅は一歩も動くことが出来ませんでした。
ふり向いて見ると「おれは寺を出るとき母の用意したお膳を足げりにして来た天罰を受け、火の海の地獄に堕ちて行く」と教傅が大声をあげて苦しみもがいております。
友人がかけ寄り助けようと引き出しましたが、教傅の腰から下が、炭のように焼けただれており、息を引き取ってしまいました。
それからも教傅の引き込まれたところには泥流がブツブツと沸いていましたが、いつしか山津波に埋まってしまった。
その後、那須湯元の有志が、享保五年に地蔵を建立して供養を行い、親不孝のいましめとして参拝する者が後を断たなかった、と言うことです。
親は大切にってことですね
 千体地蔵
千体地蔵
こちらは手の大きなお地蔵さんがビッシリ並んでいて異様な光景です
この、お地蔵さん群は実は現在進行形なのだそうです
地元の伝統工芸士の方が、今も千体目指して、石を削り作っているのだそうです
現在で700数十体あるそうです
凄いな~、日々の積み重ねは大切ってことですね
そして、奥にある殺生石に到着
 ここ一帯が火山ガス噴出地帯になっていて立ち入り禁止になっています
ここ一帯が火山ガス噴出地帯になっていて立ち入り禁止になっています
 殺生石とは、その名前の通り、近づいた生き物を殺すことから付いた名前ですが
殺生石とは、その名前の通り、近づいた生き物を殺すことから付いた名前ですが
昔から能や歌舞伎などで語られていたり、今だと漫画だとかの元になっていたりする有名な伝説が、この石の由来と云われています
 白面金毛九尾の狐
白面金毛九尾の狐
その昔、九尾の狐は中国の王の后に化けて悪行を尽くし、その後インドへ渡り太子の后に化け再び悪行を尽くしたのち、ある夜突如姿を消しました。
その数百年後、遣唐使の船で日本に渡り玉藻前と呼ばれる女性に化け鳥羽院の側に仕え、やがてはこの世を治め、人の世を滅ぼそうと企んでいました。
ところが、陰陽師・阿部泰成にその正体を見破られ、当時は住む人も少なかった那須野へと飛び去り悪事を続けました。
それを知った朝廷は「九尾の狐退治の勅命」を下し、勅命によって那須へ集結した軍勢に追い詰められた九尾の狐は、ついに鏑矢で射止められ、巨大な毒石に姿を変えました。
毒石に姿を変えてからも、その毒は村人たちに害を及ぼし続けました。
後年、そのことを伝え聞いた名僧・玄翁和尚による一喝で石は打ち砕かれて、美作国高田(現岡山県真庭市勝山)、越後国高田(現新潟県上越市)、安芸国高田(現広島県安芸高田市)などに飛び散り、そのひとつがこの地に残り、いまだに毒気を放ち続けていると云われています。
おっかない狐が石になったってことですね~
 殺生石の隣りには神社があります
殺生石の隣りには神社があります
 その名も温泉神社
その名も温泉神社
(いかにも温泉の効能に御利益がありそうな神社ですね!)
 温泉神社の拝殿の隣りに九尾の狐が祀られております
温泉神社の拝殿の隣りに九尾の狐が祀られております
 殺生石には松尾芭蕉も訪れて「奥の細道」に書かれています
殺生石には松尾芭蕉も訪れて「奥の細道」に書かれています
「石の毒気いまだ滅びず、蝶蜘蛛のたぐひ真砂の色の見えぬ程にかさなり死す」
と書かれていて、当時はもっと噴気活動が盛んで、虫や蝶の死骸だらけだった様です
温泉神社の境内には、その時の俳句の句碑が建っています
石の香や
夏草赤く
露あつし
 神社の入り口には足湯があったので少し休憩しました
神社の入り口には足湯があったので少し休憩しました
火山ガスも温泉も地球が活動しているからこそ、生きているからこそなのでしょうね~
温泉は本当にありがたや、ありがたやです
 生きる!
生きる!
を実感出来るパワースポットですね
那須岳登山へ行く、ついでに近辺の観光と滝巡りをして来ました

那須と言えば昔から定番のスポット
栃木県那須町の那須湯本温泉付近にある火山性の噴気活動をしている場所です
硫黄の匂いがプンプンします


なんとも、いかにもな名前の石は駐車場から2,3分、歩いた所にあります

途中には、云われのあるモニュメントが幾つかあります
昔、湯守の五左ェ門さんが山に薪を採りに行き、この殺生河原で一休みしていると、2メートルを越える大きな蛇に出会いました。
大きな蛇の目は白く濁り盲の蛇で、かわいそうに思った五左ェ門さんは、これでは冬を越せないだろうと蛇のためにススキと小枝で小屋を作ってあげました。
次の年、五左ェ門さんは、湯殿開きの日に小屋に来て蛇をさがしましたが、蛇の姿はどこにもなく、かわりにキラキラと輝く湯の花がありました。
盲蛇に対する暖かい気持が神に通じ、湯の花のつくり方を教えてくれたのでした。
その後、湯の花のつくり方は村中に広まり、村人は盲蛇に対する感謝の気持を忘れず、蛇の首に似たこの石を盲蛇石を名付け大切にしたのだそうです。
生き物は大切にってことですね

昔、「教傅(伝)」と言う住職がおりました。
この教傅は生まれながらの不良少年で、心配した母がお坊さんにしようとしてこの寺に預かってもらいました。
その教傅も二十八歳になって、前の住職の跡を継ぎ、母と一緒に寺に住むようになりましたが、その行いは少しも直りませんでした。
教傅は二、三人の友人と一緒に、那須温泉に湯治に行くことになりました。
教傅は、母が朝食を用意して進めると、まだ旅路支度も出来ていないのにと悪口を言いながら、お腹をけとばしてそのまま出発してしまいました。
那須温泉に着いた教傅達はある日殺生石を見学しようと賽の河原付近まで行くと、今まで晴れわたっていた空が、俄かにかきくもり雷鳴が天地を揺るがし、大地から火災熱湯が噴出し、連れの友人はいっせいに逃げ去りましたが、教傅は一歩も動くことが出来ませんでした。
ふり向いて見ると「おれは寺を出るとき母の用意したお膳を足げりにして来た天罰を受け、火の海の地獄に堕ちて行く」と教傅が大声をあげて苦しみもがいております。
友人がかけ寄り助けようと引き出しましたが、教傅の腰から下が、炭のように焼けただれており、息を引き取ってしまいました。
それからも教傅の引き込まれたところには泥流がブツブツと沸いていましたが、いつしか山津波に埋まってしまった。
その後、那須湯元の有志が、享保五年に地蔵を建立して供養を行い、親不孝のいましめとして参拝する者が後を断たなかった、と言うことです。
親は大切にってことですね

こちらは手の大きなお地蔵さんがビッシリ並んでいて異様な光景です
この、お地蔵さん群は実は現在進行形なのだそうです
地元の伝統工芸士の方が、今も千体目指して、石を削り作っているのだそうです

現在で700数十体あるそうです
凄いな~、日々の積み重ねは大切ってことですね

そして、奥にある殺生石に到着
昔から能や歌舞伎などで語られていたり、今だと漫画だとかの元になっていたりする有名な伝説が、この石の由来と云われています

その昔、九尾の狐は中国の王の后に化けて悪行を尽くし、その後インドへ渡り太子の后に化け再び悪行を尽くしたのち、ある夜突如姿を消しました。
その数百年後、遣唐使の船で日本に渡り玉藻前と呼ばれる女性に化け鳥羽院の側に仕え、やがてはこの世を治め、人の世を滅ぼそうと企んでいました。
ところが、陰陽師・阿部泰成にその正体を見破られ、当時は住む人も少なかった那須野へと飛び去り悪事を続けました。
それを知った朝廷は「九尾の狐退治の勅命」を下し、勅命によって那須へ集結した軍勢に追い詰められた九尾の狐は、ついに鏑矢で射止められ、巨大な毒石に姿を変えました。
毒石に姿を変えてからも、その毒は村人たちに害を及ぼし続けました。
後年、そのことを伝え聞いた名僧・玄翁和尚による一喝で石は打ち砕かれて、美作国高田(現岡山県真庭市勝山)、越後国高田(現新潟県上越市)、安芸国高田(現広島県安芸高田市)などに飛び散り、そのひとつがこの地に残り、いまだに毒気を放ち続けていると云われています。
おっかない狐が石になったってことですね~


(いかにも温泉の効能に御利益がありそうな神社ですね!)
「石の毒気いまだ滅びず、蝶蜘蛛のたぐひ真砂の色の見えぬ程にかさなり死す」
と書かれていて、当時はもっと噴気活動が盛んで、虫や蝶の死骸だらけだった様です
温泉神社の境内には、その時の俳句の句碑が建っています
石の香や
夏草赤く
露あつし

火山ガスも温泉も地球が活動しているからこそ、生きているからこそなのでしょうね~
温泉は本当にありがたや、ありがたやです

を実感出来るパワースポットですね

Posted by gami at 02:36│Comments(0)
│旅
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。