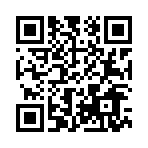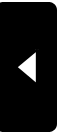2016年05月18日
岩木山神社
八甲田山登山の様子はこちらから!
奥入瀬渓流撮影練習の様子はこちらから!
十和田湖の様子はこちらから!
七滝の様子はこちらから!
岩木山登山の様子はこちらから!
2016年3月
岩木山登山を終え、岩木山の山バッチを探しに、続いて訪れたのが
岩木山神社 (wikiより)
青森県弘前市百沢の岩木山の南東麓にある神社。
別称、「お岩木さま」「お山」「奥日光」、旧社格は国幣小社で、津軽国一宮とされる。
昔から農漁業の守護神として、津軽の開拓の神として、地元の人々の祖霊の鎮まるところとして、親しまれてきた。
なお神社の参道は岩木山の登山道の1つとなっていることでも知られており、この神社の奥宮は岩木山の山頂付近にある。
社殿は、神仏習合の時代の名残りをとどめ、鎌倉時代以後の密教寺院の構造がみられる中に、桃山時代の様式を思わせる色とりどりの絵様彫刻がみられ、そうした外観が日光の東照宮を思わせるとして、「奥日光」と呼ばれるに至った。
祭神
顕国魂神(うつしくにたまのかみ)-大国主神
多都比姫神(たつびひめのかみ)-宗像三女神の湍津姫神[3]
宇賀能売神(うかのめのかみ)
大山祇神(おおやまつみのかみ)
坂上刈田麿命(さかのうえのかりたまろのみこと)
以上をまとめて岩木山大神(いわきやまおおかみ)と称する。
なお、顕国魂神、宇賀能売神については、いかなる神なのか、異説が多い。
顕国魂神については、大国主神の別称の一つとされるが、疑問の声も出ている。
歴史
創建については諸説があるが、最も古い説では、宝亀11年(780年)、岩木山の山頂に社殿を造営したのが起源とされる。
延暦19年(800年)、岩木山大神の加護によって東北平定を為し得たとして、坂上田村麻呂が山頂に社殿を再建し、その後、十腰内地区に下居宮(おりいのみや=麓宮、現在の厳鬼山神社)が建立され、山頂の社は奥宮とされた。
このときの祭神の詳細は不明だが、別天津神五代、神代七代、地神五代の集団神と推測される三柱の神であるとする説がある。
また、田村麻呂は、父の刈田麿も合祀したとされる。
寛治5年(1091年)、神宣により、下居宮を十腰内地区から岩木山東南麓の百沢地区に遷座し、百沢寺(ひゃくたくじ)と称したのが現在の岩木山神社となっている。
岩木山の山頂に阿弥陀・薬師・観音の3つの堂があり、真言宗百沢寺岩木山三所大権現と称して、付近の地頭や領主らに広く信仰された。
天正17年(1589年)、岩木山の噴火により、当時の百沢寺は全焼することとなり、以後、再建が進められることとなった。
江戸時代には津軽藩の総鎮守とされ、津軽為信・信牧・信義・信政らの寄進により社殿等の造営が進んだ。
特に、信義、信政のときに、現在の拝殿(当時は百沢寺の本堂とされた)や本殿(当時の下居宮)が再建された。
明治の神仏分離により寺院を廃止、津軽総鎮守・岩木山神社とされ、明治6年(1873年)、国幣小社に列格された。
境内
現存する社殿や楼門は江戸時代初期から元禄時代にかけて代々の弘前藩主が造営・寄進したもので、本殿・拝殿・奥門・楼門等が重要文化財に指定されている。
本殿 - 三間社流造銅瓦葺。
全面黒漆塗とする。元禄7年(1694年)建立。
拝殿 - 桁行5間、梁間5間、入母屋造平入、とち葺形銅板葺。
寛永17年(1640年)、神仏習合の時代に、百沢寺の本堂として建立された。
天正17年(1589年)の岩木山の噴火により焼失したが、慶長8年(1603年)に津軽為信により再建が始まり、寛永17年(1640年)、津軽信義のときに現在のものが完成した。
楼門 - 紅がら塗りの唐様である。
寛永5年(1628年)、津軽信枚(のぶひら)により、百沢寺の山門として建立された。
上層に十一面観音、五百羅漢像が祀られていたが、神仏分離による廃寺の際にそれらは姿を消し、階下に随神像を祀ることとなった。
狛犬 - 逆立ちの姿勢である。
祭事
大祭 -旧暦8月1日に行われる。
お山参詣(神賑祭) -重要無形民俗文化財に指定されており、岩木山の山頂にある奥宮を目指して、旧暦8月1日に行われる登拝の祭礼である。
村ごとに団体で行われ、各村の産土神の社にて一週間精進潔斎した後、五穀豊穣を祈るためお山参詣をすることとなり、白装束に身を固め、「さいぎさいぎ(懺悔懺悔)」と登山囃子を唄しながら急坂を登る。
朔日の朝日を拝するため、明け方、暗いうちから始まるものである。
駐車場から真っすぐに本殿へと伸びる境内
更に奥には、先ほど登った岩木山の頂上がどっしりと見えます
 よう、あそこまで行って来たなぁっと思います
よう、あそこまで行って来たなぁっと思います立派な楼門
そこいらの神社にあるような手水舎が無く、楼門の脇に手水所があります
 岩木山からの御神水だそうです
岩木山からの御神水だそうです中門を潜り拝殿にて参拝
 良い天気の日に登らせて貰ってありがとうございます!
良い天気の日に登らせて貰ってありがとうございます!そして、売店の人に山バッチがあるか聞くと、こちらを出して貰いました
 岩木山登山記念バッチ
岩木山登山記念バッチいつもの山バッチとは違う山バッチになりました

地元の人に「おいわき山」とか「おいわき様」と親しみ呼ばれている岩木山
その岩木山を色んな角度から撮影してみました

リンゴの木と岩木山
 リンゴの成っている時にも見てみたい景色
リンゴの成っている時にも見てみたい景色こりゃ、ホント霊峰っす

2016年04月27日
十和田湖
八甲田山登山の様子はこちらから!
奥入瀬渓流撮影練習の様子はこちらから!
2016年 3月
八甲田山を登り、奥入瀬渓流を見て、、、、、
と来れば、次に行くのは大体決まってきますが

そうです、でっかくて深い湖の十和田湖です

この辺の観光の黄金ルートっすね

十和田湖に着いたのは夕方、、、すでに土産屋は全部閉店
 平日ですからね~
平日ですからね~安達太良山の「本当の空」で有名な高村光太郎作の乙女の像
THE十和田湖の景色ですね~

乙女の像を見た後は十和田神社にお参り
明日も無事に下山出来ます様に

湖岸に戻り、少し散歩

日が傾き、色付き始め湖面を染めていきます
冬の夕方の湖って寂しいイメージでしたが、これは綺麗でしたね~

展望台からの十和田湖
 大きいっす
大きいっすすっかり晴れた八甲田山を遠望し十和田湖を後にします
2016年04月26日
奥入瀬渓流撮影練習
八甲田山登山の様子はこちらから!
2016年 3月
八甲田山に続き、訪れましたのが
八甲田の南側に広がる十和田湖からの清流が美しいスポット
奥入瀬渓流
 (こちらの滝は銚子大滝)
(こちらの滝は銚子大滝)まだまだ雪も多く遊歩道も雪の下な状態だったのですが
そんな奥入瀬渓流に、なにしに行ったかと言うと
綺麗な清流の撮影の練習

シャッタースピードを遅くすると
こんな感じに水の流れを糸を引いた様に表現

こんな水の流れも
幻想的に水が流れている様に

奥入瀬っぽい写真になります

滝下だと水しぶきが豪快に見える様に高速シャッターが良さげですね

私の大好きな場所の奥入瀬渓流

新緑の季節か、紅葉の季節に、また行きたいですね~

写真の腕をもっと上げなくちゃね!
2016年03月25日
真田宝物館
三つ峠登山の様子はこちらから!
霧ヶ峰写真練習の様子はこちらから!
2016年 2月
霧ヶ峰からの帰り道、上田市を通り帰路に着こうと思っていたのですが、上田市近辺は今年の大河「真田丸」で道の両脇に幟が立つなど賑わっておりました

折角なので真田の歴史を学ぶため、松代にある真田宝物館へと行って来ました

真田宝物館 wikiより
長野県長野市松代町にある真田氏の文化財を収蔵する市立の博物館。
真田公園内にあり、近隣には旧真田邸や文武学校がある。
真田家12代当主・真田幸治が同家の文化財を松代町に寄贈。
譲り受けた収蔵品は武具・刀剣・調度品・絵画・古文書などで、特に古文書が多く総数数万点ともいわれるが依然整理中であり実数は不明である。
新館
第一展示室 真田家の歴史
武具
旧館
第二展示室 大名道具(表道具)
第三展示室 大名道具(奥道具)
第四展示室 特別企画展示
テーマ展示
開館時間:9:00〜17:00
休館日:火曜日(祝日は開館) 燻蒸期間
入館料:一般 - 300円 小・中学生 - 120円
真田家の家紋の六文銭
松代城の模型が飾ってあります
 後ろには戸隠、高妻山ですね
後ろには戸隠、高妻山ですね真田家の文化財が見れる所からは、カメラ撮影禁止

刀剣、甲冑、書物、人物絵だったり教科書で見たことがある展示物が沢山でした

歴史好きな人には堪らなく楽しい所受け合いです

記念撮影顔出し看板
真田丸絶賛放送中!
2016年03月18日
霧ヶ峰写真練習
三つ峠登山の様子はこちらから!
2016年2月
三つ峠に登り山小屋泊を断念することとなり
それでも写真撮影の練習がしたく思い
1ヵ月前に足を運んだけど天気が悪くて登山も撮影も出来なかった霧ヶ峰へ
霧ヶ峰に着くと、すでに夜になっていたので早速夜景撮影
月が明るい日だったので見えるかなぁっと期待しておりましたが、流石に富士山は見えず写らず
 残念
残念八ヶ岳夜景
横岳、縞枯山の上に月が出ておりました
月を撮る練習もしてきました
 普通に夜景を撮ろうとすると真っ白なお月様になってしまいますが
普通に夜景を撮ろうとすると真っ白なお月様になってしまいますがクレーターの見えるお月様撮影の練習
こんな感じでお月様撮影
 三脚を使わないとブレてしまうので何回も取り直ししました
三脚を使わないとブレてしまうので何回も取り直ししましたその後、車中泊をして夜明け
 綺麗な御来光です
綺麗な御来光です流石霧ヶ峰のビューポイント、起きるとカメラを携えた人達で賑わっておりました

八ヶ岳と富士山
八ヶ岳、阿弥陀岳、赤岳、横岳
そして富士山遠望
 今日は雲ひとつ無し!
今日は雲ひとつ無し!昨晩夜景として見ていた茅野市と南アルプス

仙丈ヶ岳、甲斐駒、鳳凰、北岳がめっちゃ綺麗です

こちらは中央アルプス
北アルプス、蝶ヶ岳と常念岳
そして、最後に月と御嶽

良い写真撮影の練習となりました

まだ2月だというのに雪が全く無くなっていた霧ヶ峰
咳が止まらなく、あばらも痛いので登らず次の目的地へ
 雪無いし、、、、、
雪無いし、、、、、